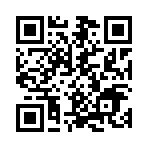2010年03月20日
レイ=ジャーディン(Ray=Jardine)とは
レイ=ジャーディン(Ray=Jardine)とは
1970年代にヨセミテ(アメリカ、カリフォルニア)で活躍したクライマー。
厳選した荷物を詰め込んだ、丈夫なパッドもフレームも入っていないバックパック。
その重さ10ポンド(約4.5Kg)を背負い、数千マイルもの距離を移動する登山スタイル=ウルトラライト・バックパッキング。
そのスタイルを体系化して広めたのは、登山家であり探検家、
またロケット工学のスペシャリストで
クライマー、カヤッカー、スカイダイバーと多彩な顔を持つレイ=ジャーディンだった。
彼は、1980年代後半から、ロングトレイルのスルーハイクに傾倒していった。
実践を積み重ねてゆく過程で、ライトウェイトでシンプルな方法論を確立し、
最終的にレイ=ジャーディンのバックパックは
ベースウェイト8.5ポンド(3.85 kg)
という域に達した。
こうした実践に基づいた方法論は改訂ごとにまとめられ、
1992年には、「PCT Hiker Handbook」を刊行し、
2000年には「Beyond Backpacking」と改訂、
ウルトラライト・ハイキング(ULH)の思想と方法論をはじめてカタチにした革命的一冊となる。
彼の実績と著作が、ウルトラライト・ハイキング(ULH)というムーブメントの起爆剤になった。

⇒「Beyond Backpacking: Ray Jardines Guide to Lightweight Hiking 」
2008年には、「Trail Lite」に改訂された。
⇒レイ=ジャーディンのサイト
2010年03月16日
ベースウェイト(Base Weight)とは
ベースウェイト(Base Weight)とは
あくまで背負う重量。
水、食料、燃料等の消費アイテムを除外したバックパックの総重量のこと。
今まで曖昧だった
「背負う重量の基準」「重量を計るべき装備類」
を明確にしたこと。
これによって
装備重量の比較、検討、改良を
ハイカーの間で共有できるようになった。
着ているもの、持っているもの、ポケット内のものは
「ウァラブル」と称して除外される。
ポケットに道具を詰め込めばベースウェイトが軽くなる。
ベースウェイトは、重さによって呼び方が分けられている。
ーTraditional 35ポンド以上(17kg~)
ーLight Weight 20ポンド以下(8~9kg程度)
ーUltra Light 10ポンド以下(4~5kg程度)
ーSub-Ultra Light 5ポンド以下(2~3kg程度)
現在の平均的な道具を選べば、
ほとんどのハイカーが「Light Weight」のクラスになる。
しかし、
10kg近い荷物を担いだことがない。
普段、担だことがない重量を背負って、
ハイキングに行くというのはとても大変なことらしい。
疲れてうつむき、せっかくの景色も見ることができない。
あげくにバテてしまって動けなくなる。
安全のために背負った装備が、かえって自分を苦しめる。
そんな寓話のようなことになりかねない。
そうならないためには、トレーニング!?
でもトレーニングのための時間が、なかなかとれない。
怪我や故障をかかえている。
そんなハイカーのためにUltra Lightがあるのだ。
日帰りも、小屋泊まりも、テント泊も、同じようなバックパックの重量で行ける世界がある。
ベースウェイトは、5kg以下が望ましい。
ハイキングは劇的に変化する。
●参考文献
Hiker's Depot
あくまで背負う重量。
水、食料、燃料等の消費アイテムを除外したバックパックの総重量のこと。
今まで曖昧だった
「背負う重量の基準」「重量を計るべき装備類」
を明確にしたこと。
これによって
装備重量の比較、検討、改良を
ハイカーの間で共有できるようになった。
着ているもの、持っているもの、ポケット内のものは
「ウァラブル」と称して除外される。
ポケットに道具を詰め込めばベースウェイトが軽くなる。
ベースウェイトは、重さによって呼び方が分けられている。
ーTraditional 35ポンド以上(17kg~)
ーLight Weight 20ポンド以下(8~9kg程度)
ーUltra Light 10ポンド以下(4~5kg程度)
ーSub-Ultra Light 5ポンド以下(2~3kg程度)
現在の平均的な道具を選べば、
ほとんどのハイカーが「Light Weight」のクラスになる。
しかし、
10kg近い荷物を担いだことがない。
普段、担だことがない重量を背負って、
ハイキングに行くというのはとても大変なことらしい。
疲れてうつむき、せっかくの景色も見ることができない。
あげくにバテてしまって動けなくなる。
安全のために背負った装備が、かえって自分を苦しめる。
そんな寓話のようなことになりかねない。
そうならないためには、トレーニング!?
でもトレーニングのための時間が、なかなかとれない。
怪我や故障をかかえている。
そんなハイカーのためにUltra Lightがあるのだ。
日帰りも、小屋泊まりも、テント泊も、同じようなバックパックの重量で行ける世界がある。
ベースウェイトは、5kg以下が望ましい。
ハイキングは劇的に変化する。
●参考文献
Hiker's Depot
2010年03月16日
エマ=ゲイトウッドとは
エマ=ゲイトウッドとは
1954年、女性初の「Appalachian Trail」(AT)スルーハイカー。
当時67歳。
食料等も含むハイキング装備を20ポンド(9Kg)以下におさえ、
ULハイカーの間で「伝説」となったグランマ。
1954年、女性初の「Appalachian Trail」(AT)スルーハイカー。
当時67歳。
食料等も含むハイキング装備を20ポンド(9Kg)以下におさえ、
ULハイカーの間で「伝説」となったグランマ。
2010年03月15日
トリプルクラウンとは
トリプルクラウンとは
3000Kmを超える3つのトレイル
「Pacific Crest Trail」(PCT)
「Continental Divide Trail」(CDT)
「Appalachian Trail」(AT)
のスルーハイク達成者の称号。
3000Kmを超える3つのトレイル
「Pacific Crest Trail」(PCT)
「Continental Divide Trail」(CDT)
「Appalachian Trail」(AT)
のスルーハイク達成者の称号。
2010年03月15日
スルーハイク(Thru-Hike)とは
スルーハイク(Thru-Hike)とは
ロングトレイルを数日~数ヶ月かけて歩き通すこと。
アメリカ・ハイキング文化の核となる考え方。
加藤 則芳氏の著書「ジョン・ミューア・トレイルを行く」が詳しい。


⇒ジョン・ミューア・トレイルを行く―バックパッキング340キロ (単行本)
シエラクラブの生みの親、「森の聖者」と呼ばれたジョン・ミューアその名を冠した山岳トレイル340キロを、ヨセミテからマウント・ホイットニーまで一気に踏破した記録。
35キロの装備を背負い、クマに出会い、ゴールデントラウトを釣り上げ、バックパッカーと意気投合!アウトドア魂の真髄がここにある。
ロングトレイルを数日~数ヶ月かけて歩き通すこと。
アメリカ・ハイキング文化の核となる考え方。
加藤 則芳氏の著書「ジョン・ミューア・トレイルを行く」が詳しい。

⇒ジョン・ミューア・トレイルを行く―バックパッキング340キロ (単行本)
シエラクラブの生みの親、「森の聖者」と呼ばれたジョン・ミューアその名を冠した山岳トレイル340キロを、ヨセミテからマウント・ホイットニーまで一気に踏破した記録。
35キロの装備を背負い、クマに出会い、ゴールデントラウトを釣り上げ、バックパッカーと意気投合!アウトドア魂の真髄がここにある。
2010年03月15日
日本のウルトラライト革命家たち
日本のウルトラライト革命家たち
軽量化だけを取り上げれば、ULHは極端で過激な数字遊びになりかねない。
しかしその核には「自然回帰」という
アウトドア・カルチャー、バックパッキング・カルチャーの原点が
純粋なかたちで在ることを忘れてはいけない。
ハイカーのアンダーグラウンド・カルチャーとして90年代後半に生まれたULH。
その潮流はハイカー自身の手で日本に紹介されてきた。
海外と交流を持ち詳細な翻訳を紹介してきた、
川崎一氏。
彼によりワンポールシェルターやハンモックシェルター、「ジェットボイル」が日本に紹介された。
大畑雅弘氏は、日本ではじめて「ウルトラライトハイキング」というサイトを開設。
エマ=ゲイトウッドの紹介、
海外トレイルの記録や充実したリンク集など、ULHのポータルサイト的意義があった。
歩きの登山をロジカルに追及した加藤英雄氏は、
日本での長距離&長期縦走の方法論を実践により集大成、
その中でレイ・ウェイの意味とその限界について的確な論評をしている。
軽量ギアを自ら使い批評する寺澤英明氏は、
客観的かつ圧倒的な情報量から多くのハイカーに影響を与え、
一つのブログ・スタイルを確立した。
日本の気候における
長期&長距離での実例の不足など、課題もあるが、
自然とつながるシンプルなスタイルとして、
日本のULHは始まったばかりである。
軽量化だけを取り上げれば、ULHは極端で過激な数字遊びになりかねない。
しかしその核には「自然回帰」という
アウトドア・カルチャー、バックパッキング・カルチャーの原点が
純粋なかたちで在ることを忘れてはいけない。
ハイカーのアンダーグラウンド・カルチャーとして90年代後半に生まれたULH。
その潮流はハイカー自身の手で日本に紹介されてきた。
海外と交流を持ち詳細な翻訳を紹介してきた、
川崎一氏。
彼によりワンポールシェルターやハンモックシェルター、「ジェットボイル」が日本に紹介された。
大畑雅弘氏は、日本ではじめて「ウルトラライトハイキング」というサイトを開設。
エマ=ゲイトウッドの紹介、
海外トレイルの記録や充実したリンク集など、ULHのポータルサイト的意義があった。
歩きの登山をロジカルに追及した加藤英雄氏は、
日本での長距離&長期縦走の方法論を実践により集大成、
その中でレイ・ウェイの意味とその限界について的確な論評をしている。
軽量ギアを自ら使い批評する寺澤英明氏は、
客観的かつ圧倒的な情報量から多くのハイカーに影響を与え、
一つのブログ・スタイルを確立した。
日本の気候における
長期&長距離での実例の不足など、課題もあるが、
自然とつながるシンプルなスタイルとして、
日本のULHは始まったばかりである。
タグ :ULH
2010年03月14日
「ベースウェイト」という考え方
「ベースウェイト」という考え方
ULHで画期的なことは、
背負う重量の「計測範囲」と「目安」が提示されたこと。
これにより、重量の比較、検討、改良がハイカー間で共有できるようになった。
何をどこまで軽くすれば快適になるのか?
計測範囲は「ベースウェイト」、
目安は「10ポンド(4.5Kg)」
スルーハイクでは、消費したものを補給しながら歩く。
そこで、消費、補給される水、食料、燃料を除いた装備重量を
ベースウェイトとするのだ。
その目安には様々な意見があるが、
アメリカでは10ポンド(4.5Kg)前後に落ち着いている。
レイ=ジャーディン自身は、
最終的に8.5ポンド(3.85Kg)というベースウェイトで歩いている。
環境の異なる日本に容易に当てはめることは、できないが、
日本のウルトラライト志向のハイカーも、
無雪期5Kg前後を目標としているようだ。
そのように
「徹底した軽量化」は
ULHの大きな特徴だ。
しかし、レイ=ジャーディンは、著書「Beyond Backpacking」の冒頭で、
軽量化の本当の目的である、哲学的、思想的な命題を強調している。


⇒「Beyond Backpacking: Ray Jardines Guide to Lightweight Hiking 」
家財道具を全て持ち出すようなスタイルでは身の回りが道具であふれかえり、
自然との距離が遠ざかってしまう。
本当にその道具がないと
自然の中に行けないのだろうか?
安全のために、と多くを背負いすぎた結果、
重さに負けて歩けなくなる。
それでは、あまりに辛すぎる。
ハイキングやキャンプは、自然の中に身を置き、
自然を感じるためのもの。
自ら運べるものを運び、優しく自然の中を歩き、自然の営みに気付き、
そして自然との関わりを考える。
そのためには自然をダイレクトに感じる必要がある。
だからこそ、
必要最小限にして
シンプルな道具を選ぶのだ。
ULHで画期的なことは、
背負う重量の「計測範囲」と「目安」が提示されたこと。
これにより、重量の比較、検討、改良がハイカー間で共有できるようになった。
何をどこまで軽くすれば快適になるのか?
計測範囲は「ベースウェイト」、
目安は「10ポンド(4.5Kg)」
スルーハイクでは、消費したものを補給しながら歩く。
そこで、消費、補給される水、食料、燃料を除いた装備重量を
ベースウェイトとするのだ。
その目安には様々な意見があるが、
アメリカでは10ポンド(4.5Kg)前後に落ち着いている。
レイ=ジャーディン自身は、
最終的に8.5ポンド(3.85Kg)というベースウェイトで歩いている。
環境の異なる日本に容易に当てはめることは、できないが、
日本のウルトラライト志向のハイカーも、
無雪期5Kg前後を目標としているようだ。
そのように
「徹底した軽量化」は
ULHの大きな特徴だ。
しかし、レイ=ジャーディンは、著書「Beyond Backpacking」の冒頭で、
軽量化の本当の目的である、哲学的、思想的な命題を強調している。

⇒「Beyond Backpacking: Ray Jardines Guide to Lightweight Hiking 」
家財道具を全て持ち出すようなスタイルでは身の回りが道具であふれかえり、
自然との距離が遠ざかってしまう。
本当にその道具がないと
自然の中に行けないのだろうか?
安全のために、と多くを背負いすぎた結果、
重さに負けて歩けなくなる。
それでは、あまりに辛すぎる。
ハイキングやキャンプは、自然の中に身を置き、
自然を感じるためのもの。
自ら運べるものを運び、優しく自然の中を歩き、自然の営みに気付き、
そして自然との関わりを考える。
そのためには自然をダイレクトに感じる必要がある。
だからこそ、
必要最小限にして
シンプルな道具を選ぶのだ。
タグ :ベースウェイト
2010年03月14日
ウルトラライト・ハイキングに大きな影響を与えたハイカー
ウルトラライト・ハイキングに大きな影響を与えたハイカー
スルーハイクの歴史には、エマ=ゲイトウッドという伝説的ハイカーがいるが、
現在に大きな影響を与えたハイカーが、
レイ=ジャーディンだ。
彼の実績と著作が、ウルトラライト・ハイキング(ULH)というムーブメントの起爆剤になった。


⇒「Beyond Backpacking: Ray Jardines Guide to Lightweight Hiking 」
70年代にクライマーとして活躍したレイは、
80年代後半からロングトレイルのスルーハイクに傾倒、
驚異の日数で次々とスルーハイクを成功させる。
その実践から生まれた方法論は、「レイ・ウェイ」と呼ばれ、
90年代に書籍として著わされる。
彼自身は、「ウルトラライト」という表現を用いなかったが、
この急進的方法はハイカーに大きな影響を与え、
思想面も含めたULHというムーブメントを誕生させるのである。
スルーハイクの歴史には、エマ=ゲイトウッドという伝説的ハイカーがいるが、
現在に大きな影響を与えたハイカーが、
レイ=ジャーディンだ。
彼の実績と著作が、ウルトラライト・ハイキング(ULH)というムーブメントの起爆剤になった。

⇒「Beyond Backpacking: Ray Jardines Guide to Lightweight Hiking 」
70年代にクライマーとして活躍したレイは、
80年代後半からロングトレイルのスルーハイクに傾倒、
驚異の日数で次々とスルーハイクを成功させる。
その実践から生まれた方法論は、「レイ・ウェイ」と呼ばれ、
90年代に書籍として著わされる。
彼自身は、「ウルトラライト」という表現を用いなかったが、
この急進的方法はハイカーに大きな影響を与え、
思想面も含めたULHというムーブメントを誕生させるのである。
2010年03月14日
”UL”(ウルトラライト)ハイキングとは何か・・・
”UL”(ウルトラライト)ハイキングとは何か・・・
アウトドアシーンで注目されている「UL(ウルトラライト)」についていろいろ調べてみた。
ウルトラライトが生まれた背景。
アメリカの広大なトレイルを春から秋にかけてのワンシーズンで踏破することを
スルーハイク、
そのハイカーをスルーハイカーと呼ぶ。
ウルトラライトハイキング(ULH)とは、
こうしたスルーハイクで培われてきたハイキングスタイルのこと。
数千キロものスルーハイクは、4~5ヶ月、
入門的なジョン・ミューア・トレイルでさえ全工程は約340Km。
20日間ほどかけて歩く。
こうした距離を歩くには身体への負担が少ないにこしたことは、ない。
少しでも体力に余裕を持たせて歩きたい。
そのためスルーハイカーは、「歩く」ということに、
装備も方法も特化させていく。
その最大の手段が「徹底した軽量化」なのだ。
2010年03月14日
ひと昔前なら、20kg背負って山歩き!
ひと昔前なら、20kg背負って山歩き!
が普通でした。
でも、時代が変わり、
最近の旅人は10kg以下の軽~い荷物で山を楽しんでいるようです。
その背景には、
「ウルトラライト」なるムーブメントが。。。
はて、”UL”(ウルトラライト)とは、いったい何?
が普通でした。
でも、時代が変わり、
最近の旅人は10kg以下の軽~い荷物で山を楽しんでいるようです。
その背景には、
「ウルトラライト」なるムーブメントが。。。
はて、”UL”(ウルトラライト)とは、いったい何?